これからの時代にあった出口戦略を考える新築戸建て住宅
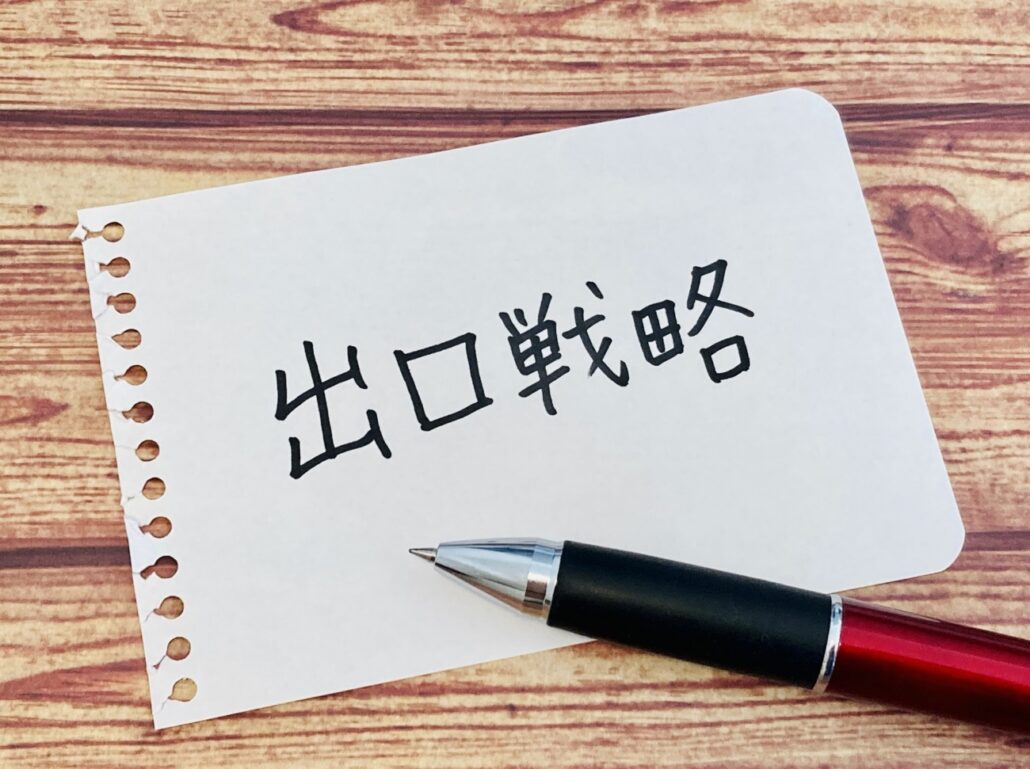
新築戸建て住宅を取得する人の多くは、理想の生活を手に入れるために購入・建築するのではないでしょうか。しかし、近年は理想の生活だけでなく、出口戦略まで検討してから取得する人が増えています。
それではなぜ出口戦略を考えるようになったのか、どのように戦略を立てればよいのでしょうか。
本記事では出口戦略を考えるべき理由、戦略を検討するときのポイントについて解説します。
新築戸建て住宅を購入・建築するときに出口戦略を考えるべき理由
近年は少子高齢化による人口減少やインフレによる物価上昇により、不動産を取り巻く環境が大きく変化し、新築戸建て住宅は住むだけのものと考えるわけにはいかなくなっています。
たとえば、内閣府の「第1節 高齢化・人口減少の意味」によると、少子高齢化により日本の人口は2050年までに2,000万人ほど減るといわれています。不動産は需要と供給のバランスで価格が決まるため、人口が減るほど需要も少なくなって価格が落ちます。需要の低い立地にある家を取得すると資産価値の下落を招く原因になりかねません。
また、近年はインフレの影響を受けて物の値段が上昇しており、相対的にお金の価値が下落しています。2023年から2024年にかけて4%を超えるインフレ率となり、一気に物の値段が上がりました。2025年は緩やかであるもののインフレが続くと見込まれています。
不動産は物でありインフレ率に応じて資産価値が高まる傾向にあるため、現金を貯蓄しておくよりも不動産に換金したほうがよいと考える人がいても不思議ではありません。
このような理由から資産としての不動産が注目されるようになり、どのように不動産価値を活かすのか考える人が増えています。
新築戸建て住宅における出口戦略のパターン
新築戸建て住宅における出口戦略の主なパターンは、以下のとおりです。
- 売却
- 賃貸
- 相続
パターンによって出口戦略が変わる可能性もあるため、まずはパターンの内容を理解しておきましょう。
売却
主な出口戦略として検討されるのは売却です。
新築戸建て住宅を取得し、いつまでに売却するのか、売却した際にはいくらで売れるのか考慮します。
新築戸建て住宅といっても、いつまでも住めるわけではなく寿命があります。また、老後といったライフスタイルの変化によって住まいを変えなければならないケースもあるでしょう。
このようなケースに対応するには、売却時期と売却金額の把握が不可欠となります。
賃貸
新築戸建て住宅が賃貸需要のある場所に立地している場合、第三者に貸す方法を選択する方がいます。
賃貸する期間や想定賃料、想定費用を算出すれば、どの程度の利益が得られるのかがわかります。
ただし、賃貸という選択肢は、安定した需要がある物件でなければ成り立たず、またオーナーとしての管理・経営能力も求められる点に注意が必要です。
相続

資産を残したいと考えている人は、相続で配偶者や子どもに受け継いでもらいます。
長期優良住宅のように長期間価値が残る建物や、土地の価値が上昇している土地を所有している場合に有効です。
ただし、価値が高すぎると相続税の課税対象となるため、出口戦略を検討する際には相続対策までおこなう必要があります。
新築戸建て住宅における出口戦略を検討するときのポイント
新築戸建て住宅における出口戦略を検討するときには、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 主要駅が近いところに住む
- 人口が増えている地域で探す
- 高性能な住宅を取得する
- 独特な間取り・デザインを採用しない
それでは、どのようなポイントを押さえればよいのかみていきましょう。
主要駅が近いところに住む
主要駅周辺のような利便性のよい地域は人が集まりやすい傾向にあり、需要低下による資産価値の減少を抑えられます。
主要駅が近くにあれば通勤や通学に便利ですし、駅の周辺には買い物施設やクリニックなど生活利便施設の利用にも便利です。そのため、単身世帯・ファミリー世帯・高齢世帯いずれの世帯でも住みやすい地域が形成されます。
このような地域は人口が減りにくいため、不動産価値を維持するのに適しています。
人口が増えている地域で探す
人口が増えている地域の不動産需要は高く、資産価値を保ちやすい立地といえます。
人口が増加している地域では買い物施設や医療施設などが整備され、より生活しやすい環境となります。しかし、開発できる土地には限りがあり、居住希望者をすべて受け入れる体制を整えるのは困難です。
住みやすい街に住みたいという人が増えるものの、受け入れられる人数に上限があることで居住に対する競争が生まれて不動産価格が上昇します。
このサイクルを繰り返す地域は資産価値の減少が発生しにくく、売却・賃貸・相続のどの出口戦略でも検討しやすくなります。
高性能な住宅を取得する
高性能な住宅は価値の減少が緩やかで売却しやすく、相続しても価値のあるものを受け継がせられます。
日々建築技術は向上しており、取得する人の家に対する意識も高まっています。数十年後の住宅事情にも対応できるような高性能な住宅を取得すれば、売却や賃貸できる可能性が高いといえるでしょう。
なお、高性能な住宅とは長期優良住宅や低炭素住宅、ZEH水準の住宅など省エネ住宅を指します。省エネ住宅は長期間居住することを前提に設計されており、メンテナンスのしやすさを追求したり、耐久性の高い建築材料で建築されたりしているため一般的に寿命が長いといわれています。
独特な間取り・デザインを採用しない
居住性にこだわりすぎ、独特な間取りやデザインを採用すると売却や賃貸がうまくいきません。
不動産は、需要と供給のバランスによって価格が増減します。いくらよい立地にある新築戸建て住宅だとしても、住む人を限定するような間取りやデザインでは需要が低下して価格も下落するかもしれません。
たとえば、まったく間仕切りのない広大なスペースや、浴槽が必要ないと考えシャワースペースしか設けないなどです。特殊なスペースは万人受けしないため、需要が低くなると考えておくとよいでしょう。
新築戸建て住宅における出口戦略を検討するときの注意点

出口戦略を検討するときに注意すべきポイントは、以下の3つです。
- 居住性を考慮する
- 家族に適した立地を選ぶ
- 頭金を貯蓄しておく
注意点を理解すれば、適切な出口戦略を策定できるはずです。
居住性を考慮する
新築戸建て住宅を取得する際には、まず居心地のよい住宅かどうか判断しましょう。
生活動線がしっかりしておらず毎日の洗濯干しで重量のある衣類を1階から2階まで運ばなければならない、リビング横の寝室でうるさくて眠れないなど生活するなかで不満が溜まります。
いくら駅前の資産価値が高い新築戸建て住宅だとしても、日々の生活に不満を抱いてしまっては意味がありません。出口戦略を立てるなら、不動産価値だけでなく居住性まで考慮しておく必要があります。
家族に適した立地を選ぶ
出口戦略は家族のことも考えて検討しましょう。
たとえば、資産価値を考えるのであれば、主要駅周辺の利便性が高い立地の新築戸建て住宅を取得したほうがよいと考えられます。しかし、主要駅の周辺は繁華街になっていることが多く、騒音が発生したり治安が悪かったりするかもしれません。小さい子どもがいる家庭や、静かな場所に住みたい人にとっては生活に適さないおそれがあります。
家族に適さない立地で出口戦略を検討した場合、家族に不満が溜まってしまったり、危険な目にあわせたりする可能性もあると考えておくことが大切です。
頭金を貯蓄しておく
出口戦略を成功させるために、頭金を貯蓄してなるべく住宅ローンの借入額を減らしましょう。
資産価値の高い立地を選択したり、高性能な住宅を取得したりすると購入・建築費用が高額になりがちです。取得費用が身の丈にあっていないと、高額な住宅ローン借入額となって滞納する原因となります。
また、住宅ローンの残額が資産価値よりも多いと売却できず、そもそも住宅ローンが少しでも残っていると賃貸物件にすることもできません。
このように住宅ローンは出口戦略に大きな影響を与えるため、頭金を用意してなるべく早く完済する計画を立てましょう。
まとめ
不動産を取り巻く環境は日々変化しており、現在は住まいだけでなく資産として保有する方が増えています。資産として保有するなら出口戦略を検討しなければならず、不動産価値が高い物件の特徴を理解していかなければなりません。
また、資産性だけを考慮して出口戦略を検討しても成功しないため、居住性の高い不動産や家族に適した建物は何か検討したうえで実行しましょう。総合的に判断すれば、よりよい出口戦略を立てられるはずです。









を分かりやすく解説-1-180x180.jpg)



