私たち離婚しました…。住宅ローンはどうなる?

住宅ローンを利用して、自宅を購入した後に離婚すると「残っている住宅ローンはどうなるの?」と気になる人も多いのではないでしょうか。離婚時に住宅ローンが残っていると大きなトラブルになるおそれもあるため、どうなるのか知っておくべきでしょう。
本記事では、離婚時に住宅ローンがどうなるのかについて解説します。記事の後半では、離婚時の住宅ローン問題の解決方法も紹介していますので、最後までご覧ください。
離婚時に残った住宅ローンについて確認すべきポイント
離婚時に残った住宅ローンについて確認すべきポイントは、次の3点です。
- 家の名義人
- 住宅ローンの残債額
- 住宅ローンの契約内容
上記のポイントを確認しておかないと、離婚時の住宅ローンの問題を解決できません。どのような項目を確認すればいいのか、どのように確認するのか解説します。
家の名義人
離婚で自宅を売るのは名義人しか売却できないため、家の名義人を確認します。
家の名義人は法務局で、自宅の「登記簿謄本(全部事項証明書ともいう)」を取得すればわかります。取得するには、1通につき600円の手数料が必要です。
登記簿謄本には、住宅ローンの借入額や所有者名などの情報が記載されています。自宅の名義人が自分でない場合、家の売却はできません。また、共有持分がついているのであれば、共有者全員の承諾がないと家は売れません。
住宅ローンの残債額
離婚時に自宅を売却する場合、住宅ローンの残債額の確認が必要です。
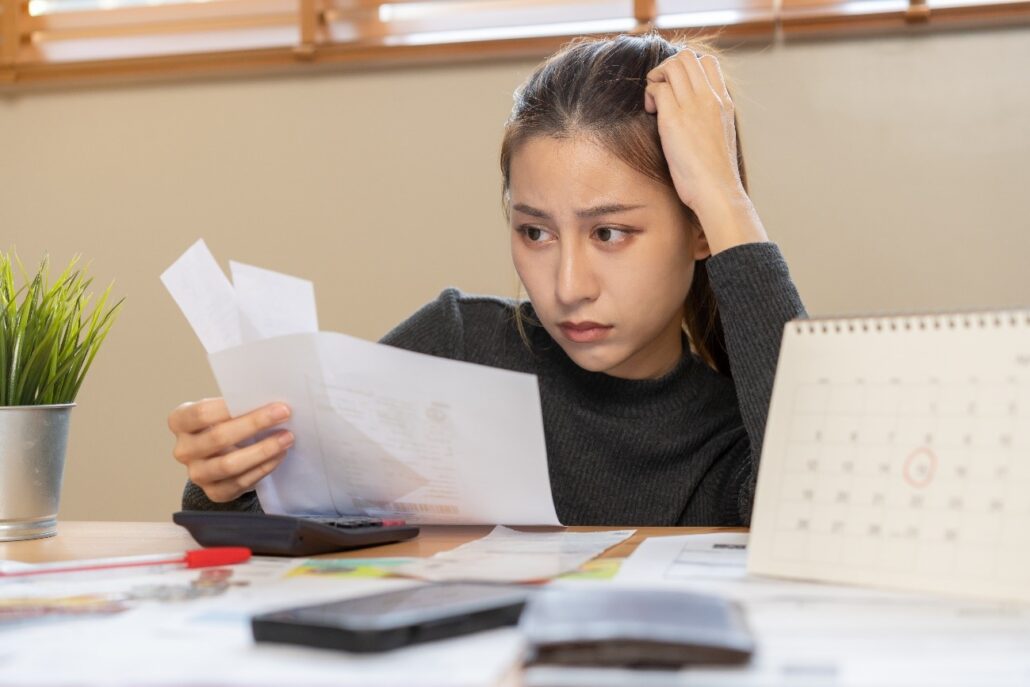
不動産を売却する場合、住宅ローンを全額返済しなければなりません。全額返済できるか確認するには、住宅ローンの残債額の確認が不可欠です。
住宅ローンの残債額は、融資してくれた銀行に問い合わせて確認するか、郵送されてくる住宅ローンの年末残高表を確認すればわかります。自宅の売却価格よりも住宅ローンの残債額が少なければ問題ないものの、残債額のほうが多い場合は売却するのに工夫が必要です。
売却するときの工夫については、後述します。
住宅ローンの契約内容
離婚する際には、住宅ローンの契約内容を確認しましょう。
住宅ローンの契約内容によっては、離婚して退去してもローンを返済することになってしまいます。
住宅ローンの契約内容は、主に次の3種類です。
- 夫婦の片方の1人が住宅ローンの返済をするタイプ
- 夫婦の片方の1人が返済するものの返せなくなった場合、もう片方の人が返済するタイプ(連帯保証型)
- 夫婦が2人で住宅ローンを全額返済するタイプ(連帯債務型)
自分が住宅ローンを返済していないとしても、連帯保証型や連帯債務型の場合、返済者がローンを返せなくなったときには自分が返さなければならなくなります。状況によっては住宅ローンの返済を金融機関から要求されるケースもあるため、契約内容は確認しておかなければなりません。とくに現在、返済している人の資力があまりないときは要注意です。
離婚時にどちらかが住み続けるには
離婚時、自宅に夫婦のどちらが住み続ける場合、次のように名義によって方法が変わります。
- 単独名義の場合
- 共有名義の場合
ここからは、単独名義の自宅に住み続けるケースと、共有名義の自宅に住み続けるケースに分けて解説します。
単独名義の場合
単独名義とは、1人で1つの不動産を所有している状態です。
自分の名義であれば、離婚後もそのまま住み続けてもかまいません。しかし、問題なのは、相手方の単独名義で、自分だけが自宅に残るケースです。他人の家に住む状態と変わりないため、離婚後に相手方の家に住み続ける際には、基本的に家賃を払って借りなければなりません。きちんと賃貸借契約書を締結して家賃を支払わないと、不法占拠といわれてしまうおそれもあります。
共有名義の場合
共有名義とは、1つの不動産を複数の人が所有している状態です。
共有不動産には自分の名義が一部あるにしても、ほかの人の名義が入った家に住むことになってしまいます。権利が不安定な状態になるため、トラブルが発生しやすい状況です。
共有名義で住まざるを得ない状況であれば仕方ないものの、できれば共有持分を相手方に購入してもらったり贈与したりするなど対策を講じたほうがいいでしょう。ただし、対策を講じるには法的な知識が必要であるため、弁護士に相談しつつ進めることが大切です。
離婚時に自宅を売却するには

離婚時に自宅を売却する場合、次のように住宅ローンの残債額によって対応が異なります。
- アンダーローンの場合
- オーバーローンの場合
ここからは、住宅ローンの残債額が自宅の売却にどのように影響するのか解説します。
アンダーローンの場合
アンダーローンとは、不動産の売却価格よりも住宅ローンの残債額が「少ない」状態です。
不動産の売却価格が住宅ローンの残債額より多ければ、売ったお金で住宅ローンを全額返済できます。そのため、アンダーローンの場合は問題なく、自宅の売却が可能です。売却して残ったお金は、財産分与して半分ずつ受け取れます。
オーバーローンの場合
アンダーローンとは、不動産の売却価格よりも住宅ローンの残債額が「多い」状態です。
金融機関は住宅ローンを全額返済しないと、担保にした不動産の売却に承諾してくれません。売却しても残ってしまった住宅ローンの残額と、同額の自己資金を用意すれば売却は可能です。しかし、自己資金を用意できる人は少なく、売却を諦めてしまう人も少なくはありません。
自己資金が用意できない場合、「任意売却」という方法を利用すれば売却できます。ただし、任意売却を実行するには専門的な知識が必要であり、取り扱える不動産会社が限られます。不動産会社に任意売却の相談をする際には、任意売却の実績を確認することが大切です。
離婚時の住宅ローンについての注意点
離婚時の住宅ローンについては、次の点に注意しなければなりません。
- 売却中も返済しなければならない
- 住宅ローンが考慮されて養育費が減る
- 自宅が競売になる
住宅ローンが残っていると、さまざまな影響を受けてしまいます。どのような影響を受けるのか確認し、スムーズな売却を実現していきましょう。
売却中も返済しなければならない
住宅ローンは全額返済するまで、毎月返し続けなければいけません。
しかし、不動産の売却には半年以上かかるケースがあり、売却中も住宅ローンの返済は続きます。余裕をもったスケジュールで売却しないと、返済できなくなってしまうおそれもあります。
離婚時にお金の余裕がないと感じるのであれば売却費用だけでなく、売れるまでに住宅ローンの返済費用がどの程度かかるのかも計算しておくといいでしょう。
住宅ローンが考慮されて養育費が減る
ローンを返済していない人が離婚後に居住し続ける場合、養育費が減るケースもあります。
住宅ローンの返済と養育費の支払いが重なると大きな負担となること、住まいのために払っている費用は養育費の一部として考慮されることから養育費が減額されてしまうわけです。
養育費をあてにしている場合、減額されると生活がかなり苦しくなるため、住宅ローンの返済をしていない家に住み続けるときには注意が必要です。
自宅が競売になる
長期間にわたって住宅ローンの返済が滞ると、自宅が競売になってしまいます。
住宅ローンの返済が一定期間にわたって滞納した場合、金融機関は貸したお金を回収すべく競売の手続きを取られてしまうため注意しなければなりません。住んでいる人が住宅ローンを返済していない人だとしても、手続きが進んでしまうといずれ強制退去の手続きまでおこなわれるおそれがあります。
他人名義の家に住むのはリスクであることを理解し、住宅ローンを滞納されてしまったときの対応を考えておくことが大切です。

離婚時の住宅ローン問題の解決方法
離婚時の住宅ローン問題は、次のように解決します。
- 住宅ローンの借り換える
- 離婚の専門家に相談する
住宅ローンは離婚時に問題になりやすいため、解決方法を理解したうえで進めていきましょう。
住宅ローンの借り換える
自宅の名義が共有になっていたり、住宅ローンの残額が多すぎたりする場合、借り換えローンを検討しましょう。
借り換えローンとは、現在借りているローンをほかの金融機関から借りたお金で返済し、あらたに借りた金融機関に返済するローンです。
ローンを借り換えれば共有名義の問題が解決し、オーバーローンでも自宅を売却できます。ただし、借り換えローンを利用するには、手数料や抵当権設定などの費用がかかるなど注意事項もあります。借り換えを検討する場合、金融機関と相談したうえで進めていきましょう。
離婚の専門家に相談する
離婚時に法的な問題が起きそうであれば、早めに弁護士といった離婚の専門家に相談しましょう。
離婚について問題が起きてしまうと、感情的になりなかなか解決できません。争っている間にも住宅ローンは返済しなければならないため、問題が発生しそうな状況になった時点で相談すべきです。
まとめ
離婚しても住宅ローンは残ったままとなり、誰が返済していくのか問題になってしまいます。また、返済せずに自宅を売却する方法もありますが、住宅ローンの残債額によっては売却も困難になってしまいます。
離婚時の住宅ローンは多くの問題を引き起こすため、どのようなトラブルになるのか、解決するにはどうしたらいいのか理解しておくことが大切です。
離婚協議が長引いてもいいことはないと考え、早めに対処していきましょう。どうしてもトラブルが解決できないのであれば、早めに弁護士に相談するのも大切なことです。










を分かりやすく解説-1-180x180.jpg)


