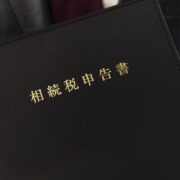子供から高齢者まで安心・安全・快適に生活できるバリアフリー住宅とは

「バリアフリー住宅とはどのような住宅なの?」「バリアフリー住宅は子供にも優しいって本当なの?」というように、バリアフリー住宅について知りたいという人も多いことでしょう。
バリアフリー住宅は段差がなく、設計によっては子供にも優しい住宅になりえます。
本記事ではバリアフリー住宅とは何か、メリット・デメリット、子供目線で考えた設計などについて解説します。子供から高齢者まで快適な住宅を建築したいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。
バリアフリー住宅とは
バリアフリー住宅とは「バリア(障壁のこと)」がない住宅です。
建築基準法にはバリアフリー住宅についての定義はなく、一般的に次のような住宅をバリアフリー住宅と呼びます。
- 段差がない住宅
- スロープや幅の広い廊下で車椅子が無理なく通過できる住宅
- ドアの開閉がしやすいように工夫されている住宅
- 室内の温度差を抑える機能をもつ住宅 など
上記のようにバリアフリー住宅とは、通常の住宅での生活が困難な人でも生活しやすい住宅です。一般的に高齢者の住みやすい住宅をバリアフリー住宅と呼ぶ傾向があるものの、子供に優しい設計でもバリアフリー住宅と呼びます。
バリアフリー住宅の需要は高く、新築時だけでなくリフォームでバリアフリー化する人も多くいます。
バリアフリー住宅にするメリット
バリアフリー住宅にするメリットは、次のとおりです。
- 事故の防止になる
- 車椅子でもスムーズな移動ができる
- 既存住宅等のリフォームに係る特例が受けられる
住宅をバリアフリー化すると、事故が防止できたり生活のストレスを軽減できたりします。ここからは、バリアフリー住宅のメリットについて詳しく解説します。
事故の防止になる
バリアフリー住宅だと、通常の住宅に比べて転倒事故の発生率を抑えられます。
消費者庁の調べによると65歳に起きた不慮の事故のうち、令和3年に起きた転倒・転落・墜落による死亡事故は9,500人を超えているそうです。転倒・転落は交通事故の4倍ともいわれており、ほとんどが同一平面上でのつまずきやスリップ、よろめきでした。
このように高齢者の転倒事故は全国で多く発生していますが、バリアフリー住宅であれば段差がほとんどなく事故発生率を下げることが可能です。
車椅子でもスムーズな移動ができる

バリアフリー住宅なら、車椅子でもスムーズな移動が可能です。
標準的な住宅の廊下の幅は平均736mmに設定されていますが、車椅子の形状・寸法はJIS規格により手動車椅子の幅は630mm以下、電動車椅子の幅は700mm以下です。そのため、標準的な住宅だと車椅子の通行が困難になってしまいます。
車椅子生活になったにもかかわらず、車椅子が通れない住宅だと住むこと自体できなくなるおそれもあります。しかし、バリアフリー住宅では部屋の開口部を800mm程度、通路スペースを900mm程度に設計するため、車椅子でも移動が容易です。
既存住宅等のリフォームに係る特例
既存住宅をバリアフリー化工事すると、既存住宅等のリフォームに係る特例を受けることが可能です。
一定のバリアフリー化工事を子育て世帯がおこなった場合、所得税が最大で20万円控除されます。
既存住宅等のリフォームに係る特例を受けるには、利用者の条件、工事の条件、期限などがあります。内容が複雑であるため利用を検討するときには、必ずリフォーム業者に既存住宅等のリフォームに係る特例が利用できるか確認しましょう。
バリアフリー住宅にするデメリット
バリアフリー住宅にするデメリットは、次のとおりです。
- 大きな敷地が必要になる
- 災害に弱くなるケースがある
- 建築費が高くなる
バリアフリー住宅にはメリットが多いものの、デメリットもあります。バリアフリー住宅の建築や、リフォームをするときにはデメリットも理解しておきましょう。
大きな敷地が必要になる
バリアフリー住宅を建築するには、大きな敷地が必要です。
バリアフリー化するには、住宅内の廊下を広くしたり、道路から玄関までのスロープを長くしたりしなければなりません。住宅内の廊下を広くするには建物を大きくしなければならず、スロープを長くするには大きな敷地が必要です。
バリアフリー住宅は狭小地に建築しにくいという面があるため、都心部に建築すると高い土地代金を払わなければならなくなってしまいます。
災害に弱くなるケースがある
バリアフリー住宅は、災害に弱い一面があるため注意しなければなりません。
バリアフリー住宅は玄関の段差をなくしてしまうことにより、浸水被害にあいやすくなってしまいます。
一般的に浸水の可能性が高い地域では基礎を上げて建物を高くしたり、盛土をおこなったりして土地を上げます。このような対策をして浸水被害を最小限に抑えるわけです。
しかし、基礎を上げるなどの工事をしてしまうと、段差が発生してバリアフリー住宅とは呼べない建物になるおそれがあります。
建築費が高くなる
バリアフリー住宅の建築費は、通常の住宅よりも高額になりがちです。
バリアフリー住宅は廊下の幅や浴室を広くするため、建物が大きくなり建築費用も上がります。また、手すりやスロープを設置するなど、追加での工事も必要となってしまいます。
子供目線で考えたバリアフリー設計
子供目線で考えたバリアフリー設計は、次のとおりです
- 広い洗面所・浴槽
- 滑りにくい床材
- すべての扉・窓に工夫して鍵を設置
バリアフリーの設計次第では、子供にとってよい住環境を整えることが可能です。子供目線で考えたバリアフリーがどのようなものなのかみていきましょう。
広い洗面所・浴槽

広い洗面所・浴槽は、子供がいる家庭にあっています。
子供が小さいときには両親と浴槽に入ったり、洗面所のスペースで2人が脱衣をしたりします。
また、子供が大きくなると朝、出掛ける前に洗面所が混雑してしまうことも解消が可能です。朝の急いでいるときに混雑するのはストレスであるため、できる限り広い洗面所や浴槽を設置したいものです。
滑りにくい床材
滑りにくい床材は、子供の転倒防止に役立ちます。
滑りにくい主な床材は、次のとおりです
- クッションフロア
- コルク
- フロアタイル
- タイルカーペット
滑りにくい床材は子供だけでなく高齢者の転倒も防止し、ペットのケガのためにも有用です。ただし、見た目や性能の問題もあるため、どの床材を利用するかは慎重に決めなければなりません。
すべての扉・窓に工夫して鍵を設置
すべての扉・窓に鍵を設置すれば、子供が誤って外に出ることを防止できます。
子供は窓や扉を勝手に開けて危険な場所に行ってしまうことがあります。たとえば、バルコニーや階段の踊り場などです。このような場所は、転落するおそれがあり大変危険です。
危険な箇所には扉の両側から施錠できるようにしたり、子供の手の届かない位置に鍵を設置したりするのがよいでしょう。また、扉の両側に鍵を設置する、窓の鍵を二重施錠にすることは認知症の人への対策にもなります。
高齢者目線で考えたバリアフリー設計
高齢者目線で考えたバリアフリー設計は、次のとおりです。
- 車椅子の通行を考慮
- 背の低い浴槽
- 各所に手すりを設置
一般的にバリアフリー住宅というと、高齢者向け住宅を指します。なぜバリアフリー住宅が高齢者向けなのかみていきましょう。
車椅子の通行を考慮
車椅子で住宅内を移動できるように考慮することが大切です。
高齢者になるとケガや病気で車椅子生活になるおそれが高いため、先を見越して廊下や部屋の開口部を広く設計しておきましょう。廊下や部屋の開口部は変更が難しく、変更できたとしても大掛かりな工事になりがちです。
介護費用が必要になったときに、バリアフリー化工事の費用まで捻出するのは難しいと考えておく必要があります。
背の低い浴槽
浴槽は背の低いものにすれば、転倒防止に役立ちます。
高齢者は少しの段差でつまずいたり、人によっては背の低いものしか乗り越えられなかったりします。浴槽に引っかかって溺水し、死亡してしまうケースもあるため注意しなければなりません。
背の低い浴槽に手すりも適切に設けていれば、溺水の危険性を減らせます。
各所に手すりを設置
住宅内の各所に手すりを設置すれば、高齢者も楽に生活できます。
最初から設置してある手すりは万人に向けてついているため、意外と使いにくいことがあります。生活する人の状態によって各所に手すりを設置することが大切です。
足の力が弱まっても腕の力を足せば、立てる人も多くいるため、手すりを適切な場所に設置しておきましょう。
まとめ
バリアフリー住宅とは、生活のバリア(障壁)を取り除いた住宅です。
たとえば、住宅の段差がない、通路が広いなどの住宅のことをいいます。生活に関係するバリアは多く、取り除くものによって高齢者だけでなく、子供の住環境を向上させることも可能です。バリアフリー化の詳細を理解していれば、家族全員が住みやすい空間を実現できます。
バリアフリー化はリフォーム・リノベーション・増築でもおこなえるため、現在の住まいにバリアが多いのであれば、バリアフリー化工事を検討してみてください。