いまさら聞けない「相続税」と「贈与税」について。2023年度税制改正について解説など
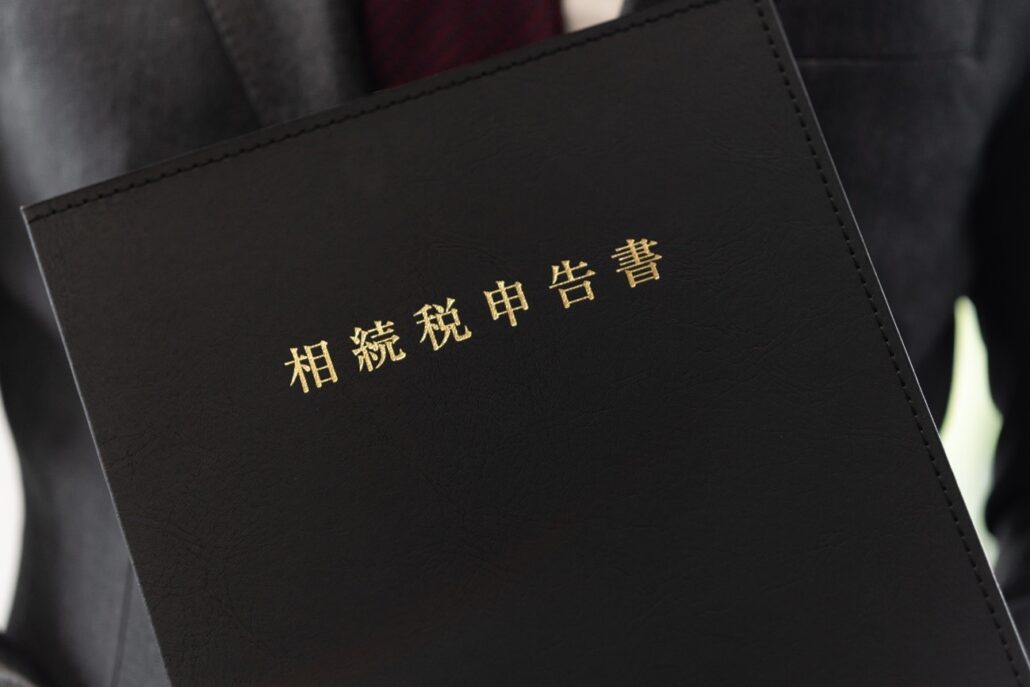
相続税や贈与税は、両方とも他人に財産を移動するときに課税されます。
財産の移動方法の違いにより、相続税・贈与税のどちらが課税されるのか変わります。どちらも税額が大きくなりがちなため、どのようなときに課税されるのか理解しておくことが大切です。
また、相続税・贈与税は2023年度の税制改正で内容が一部変更されます。変更点を知らず、税金を多く払うことのないようにしておきましょう。
本記事では相続税・贈与税とはどのような税金か、2023年度の税制改正での変更点について解説します。
相続税・贈与税とは
2023年の税制改正の話をする前に、まずは相続税や贈与税がどのような税金なのか解説していきます。
相続税とは
相続税とは亡くなった人(以下被相続人という)から財産を受け継いだ人(以下相続人という)が、取得した財産の価値分に課税される税金です。
相続税には基礎控除があり、控除の範囲内であれば課税されません。相続税の基礎控除の計算式は、次のとおりです。
相続税の基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数
つまり、相続する財産が3,000万円以下の場合は、無条件で相続税は課税されないということです。
なお、相続税の税率は次のとおりです。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
引用:国税庁「No.4155 相続税の税率」
表のとおり相続税の税率は非常に高いため、特例などを利用して相続税を抑えることが大切です。贈与税も同様ですが、相続税については税理士に相談して節税を考えていきましょう。税金は内容が複雑であり、思い込みで進めていくと取り返しのつかないことになるケースがあります。
贈与税とは
贈与税とは、贈与によって財産が他の人へ移転するときに課税される税金です。
贈与税は暦年課税方式を採用しており、年間110万円までであれば非課税です。つまり、毎年同じ人に対して110万円までの贈与をしても、贈与税は課税されません。
また、贈与税も相続税と同じく高い税率が課される税金です。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | ‐ |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
引用:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
贈与税にも特例がいくつか用意されているため、利用して税金を抑えていきましょう。
2023年度税制改正で相続税・贈与税の変更ポイント4選
相続税と贈与税にはいくつかの特例がありますが、その内容が2023年度の税制改税で変更されます。
相続や贈与を考えている人は、どのような変更点があるのか理解しておくことが大切です。
教育・結婚・子育て資金の一括贈与の期限が延長される
教育・結婚・子育て資金の一括贈与は、特例の期間が次のように延長されました。
- 教育資金の一括贈与は3年延長
- 結婚・子育て資金の一括贈与は2年延長
教育資金の一括贈与は、祖父母や父母から教育資金のために受けた、1,500万円までの贈与が非課税になる特例です。2023年3月1日までしか利用できない特例でしたが、3年間の延長が決まりました。

この特例を利用するには、銀行で結婚・子育てのための資金口座を開設し、金融機関経由で「教育資金非課税申告書」を提出すれば非課税措置が適用されます。現金をそのまま贈与しても適用されないため、注意しましょう。
また、結婚・子育て資金の一括贈与は、祖父母や父母から結婚や子育て資金のために受けた、1,000万円までの贈与が非課税になる特例です。
2023年3月31日までしか利用できない特例でしたが、2年間の期間延長が決まりました。
こちらの特例も金融機関経由で「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出すると、贈与税が非課税になります。
なお、住宅取得等資金の非課税は期間延長されませんでした。
相続時精算課税に基礎控除が創設される
2023年の税制改正により、相続時精算課税制度に基礎控除が創設されます。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の祖父母もしくは父母が18歳以上の孫や子に財産を贈与したとき、2,500万円までなら贈与税が課税されない制度です。しかし、贈与した財産は相続財産とみなされ、相続税の課税時に相続財産として計算されます。
そして、2,500万円を超える贈与をした場合、超えた部分に一律20%の贈与税が課税されます。
なお、相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税に戻すことはできなくなるため注意しましょう。
相続時精算課税制度は贈与税を課税されず贈与できますが、結局相続時に相続税が課税される制度であり、あまり利用されてきませんでした。
そのため、2023年税制改正により、相続時精算課税制度にも基礎控除が創設されることとなりました。
改正後の相続時精算課税制度では、年間110万円の基礎控除の利用が可能です。そのため、相続時精算課税制度を早く利用すればするほど、相続時の相続税計算が有利になります。
しかも、この基礎控除については、贈与税の申告不要で利用できます。
NISA制度が拡充される
2023年度の税制改正により、NISA制度が次のように拡充されます。
- 非課税保有期間が無期限になる
- つみたてNISAと一般NISAを併用できるようになる
現行はつみたてNISAの非課税保有期間は20年、一般NISAは5年です。しかし、2024年以降は非課税保有期間が無期限となり、資金が必要となるまで永久に非課税のまま保有できます。
また、つみたてNISAと一般NISAの併用が可能となり、両方合計で年間最大360万円まで非課税での投資が可能となります。
なお、NISAとは「NISA口座(非課税口座)」で、毎年一定の金額の範囲内で購入した金融商品から得られた利益が非課税になる制度です。
暦年課税の相続税加算期間が延長される
2023年度の税制改正では、贈与税の暦年課税の相続税加算期間が3年から7年に延長されることが決まりました。
贈与税で暦年課税を選択していると、年間110万円までは非課税で贈与が可能です。しかし、贈与者の死亡した日から3年以内の暦年課税は、相続財産に加算されてしまいます。
この相続税加算期間が3年から7年に延長されたことにより、相続税の納税者としては損をしてしまう可能性が高まったわけです。
そのため、うまく相続時精算課税制度を利用するなど対策が必要になりました。
相続税・贈与税についての注意点
相続税・贈与税について、それぞれ注意しておかなければいけない項目があります。ここからは、相続税・贈与税についての注意点を紹介していきます。
相続税についての注意点
相続税についての注意点は、次のとおりです。
- 生前贈与の加算を忘れてしまう
- 遺産が未分割でも期限内に申告をする
- 名義預金も申告する
相続財産には生前贈与も加算されます。前述した被相続人が死亡までの3年間におこなった贈与や、相続時精算課税制度が該当します。これらは、相続財産に加算するのを忘れやすいため注意しましょう。
相続税の申告は、相続が発生した日から10ヶ月以内に行わなければいけません。
10ヶ月以内に遺産分割協議も終わらせなければいけませんが、話し合いがうまくいかないこともあるでしょう。しかし、遺産分割協議が終わっていなくても相続税の申告は、法定相続で一旦おこなっておくことが大切です。
そして、遺産分割協議が終わったら修正申告をして、相続税を払い直して対応します。
また、名義だけ相続人の口座で、運用していたのが被相続人である名義預金も相続財産とみなされます。名義財産がある場合は、きちんと相続財産に加算して申告しましょう。
贈与税についての注意点
贈与税についての注意点は、次のとおりです。
- 贈与契約書を作成する
- 毎年異なる金額・時期に贈与をする
- 受贈者が口座を管理する
贈与は本当におこなわれたか確認できないケースも多いため、きちんと贈与契約書を作成しておきましょう。
また、毎年贈与するときには、異なる金額・時期に贈与すると税務署の調査に対応しやすくなります。
毎年同じ金額・時期に贈与をしていると、税務署に最初から「まとまった金額の贈与を計画しいたのではないか」と疑われ、贈与した金額すべてに贈与税が課税されるケースもあります。
また、贈与された財産は受贈者が自由に使えない口座に入っている場合、贈与とみなされないいため注意が必要です。
名義預金がこれに該当し、贈与した人が受贈者の口座を管理している場合です。名義預金は贈与税でも相続税でも問題になるため、極力利用しないようにしましょう。
まとめ
相続税・贈与税の税率は高く、内容を理解していないと高額な税金を課税されてしまいます。
とくに2023年度の税制改正で変更される特例を利用するときには、気を付けなければいけません。税金は特例を利用するかどうかで課税額が大きく変わるため、特例の内容をしっかりと理解しておく必要があります。
ただし、税金やその特例の内容は複雑であるため、税金について悩みがあるときには税理士に相談しましょう。税理士は税金のプロであり、相談すれば適切なアドバイスをくれることでしょう。




について-180x180.jpg)







を分かりやすく解説-1-180x180.jpg)

