将来を見据えてリフォームを想定した後悔しない家づくりのポイント
マイホームを建てるとき、つい現状の希望ばかり盛り込みがちです。しかし数年後、数十年後には子どもの自立や両親の介護、自身の老後生活などライフスタイルを変えるイベントが訪れるでしょう。
次第に自宅へ求める条件は変わるため、マイホームに違った機能を求めてリフォームを検討することになります。その際、最初から「リフォームを想定した家づくり」を行っていた住宅の方が、費用的・技術的な壁に悩まされる可能性を抑えられます。
ここでは、将来ライフスタイルが変わったときに「リフォームをしたいけど諦めるしかない」という状況にならないよう、後悔しない家づくりのポイントをご説明します。
将来の変化からリフォームを逆算しよう
マイホームのリフォームは一大イベントであり、こだわりが多いほど高額になるものだと認識されています。しかし、将来どのようなライフスタイルになるか予測し、逆算して家づくりを行えばリフォームの範囲・費用は最小限に抑えられるのです。
将来の変化として代表的なものには、どのようなケースがあるのかご紹介します。
子どもの自立・同居
家づくりを検討するタイミングは複数ありますが、やはり「理想の家庭環境を整えたい」「子育てに最適なマイホームがほしい」といった理由から、マイホーム購入を検討する場面は多いかと思います。このとき、成人した子どもの自立・同居まで想定した家づくりができれば理想的です。
子どもが自立して実家を離れる場合でも、成人以降も子どもと同居する場合でも、子ども部屋が必要となる期間は10年程度でしょう。子どもが実家を離れるなら部屋自体が使われなくなりますし、成人以降も同居するなら元々の子ども部屋を手狭に感じる懸念があるからです。
また、同居する場合には子どもが自ら自動車を持つ可能性もあるため、まとめると以下のようなリフォームを希望する可能性があります。
- 活用されなくなった子ども部屋を別の形で使いたい
- 成人した子どものライフスタイルに合わせて子ども部屋を作り変えたい
- 子どもの自動車保有に合わせて駐車台数を増やしたい
将来的に子どもがどのような人生を歩むのか予想することは難しいのですが、あらゆる可能性を考慮すれば可能な範囲で「あらゆるリフォームに対応できる家づくり」ができます。
両親の介護・自身の老後生活
もともと両親とは別々に暮らしていたものの、介護が必要になり同居にいたるケースもあります。介護が必要となるケースにおいて、高齢者ができる限り1人で行動できるような環境をつくるためには、以下のような配慮が必要です。
| 項目 | 被介護者に優しい設計とは |
| 玄関 | 屋内外をつなぐ玄関周辺にはスロープ・手すりを導入し、玄関ドアをスライドドア(引き戸)にする |
| トイレ | 便座に座るまでの導線がシンプルで、あまり体勢を変えずトイレットペーパー・水洗ボタンなどに手が届く設計にする |
| 浴室 | 浴槽へ出入りしやすいようバスタブの位置が低く、濡れても滑りづらい床・手すりの導入により転倒防止へ配慮する |
| 廊下・階段 | 見えづらい段差を解消し、手すり・照明の設置により移動時の安全性を高める |
たとえば、上記のなかには「手すりを導入する」といった言葉が複数回登場していますが、下地のない壁に設置された手すりは荷重により脱落するリスクがあります。もともと下地がある場合とは異なり、クロスを剥がし下地補強を行うなどの処理が必要となるため、クロスを張り替える分のコストがかかります。
また両親の介護だけでなく、自分たちが老後を迎えることも考慮に入れるべきです。基本的には「両親の介護」で解説したような項目の逆算が必要となります。
ただし自身の老後生活について考える分、理想の将来像について具体的なイメージが浮かびやすいかもしれません。もちろん将来的にどうなるのか未知の部分も多々ありますが、いまから夫婦で「どのような老後生活を過ごしたいのか」を話し合っても良いでしょう。
リフォームを想定した後悔しない家づくりのポイント
それぞれ、将来の家族構成やライフスタイルについてイメージしたあとは、逆算してリフォームを想定した家づくりを進めていきます。代表的なポイントとして2項目を挙げました。
自由度の高い間取りのための構造躯体を意識
リフォーム工事の際、希望として挙がる大きな変更点の1つに「間取り」があります。しかし柱・斜材などの構造躯体により、理想的な条件のリフォームを行えない可能性があるのです。
たとえば、柱には家の構造を支える重要度の高い柱と、なくても強度にあまり影響しない柱があります。そのため、将来的にリビングと個室をつなげて広い部屋に変更したい場合、重要度の高い柱があることで理想通りの空間づくりができない可能性もあります。
このようなケースを極力回避するためには、事前に「将来は部屋をつなげることを考えている」と希望を伝え、そのうえで家づくりを進めていくべきでしょう。
開口部の位置・数は慎重に検討する
ツーバイフォー工法(壁で建物全体を支える工法)を用いた住宅の場合、ドア・窓などの開口部を増やしたり位置を変えたりすることが困難です。リフォーム工事を考えるとき、つい費用面のみを問題として捉えがちですが、実は工法や構造材の特性によって実現が難しいケースもあるのです。
ツーバイフォー工法は耐震性・防火性に優れており、工期の面でもメリットがあるのですが、リフォームによる開口部の追加や間取り変更には制約が出るため注意しなければなりません。
あえて「リフォームを最小限」にする家づくりもアリ
家づくりの段階から将来のリフォームを逆算し、設計に余裕を持たせておくことも有効な手段ではありますが、最初から将来的に必要となりそうな機能を盛り込む選択肢も候補に挙がります。
たとえば「手すりは必ず設置するだろう」と予測し、初めから玄関・廊下・階段に手すりを設置するなど、多少費用はかかりますが後々に手間や支出が生じないよう行動する考え方もあるのです。例として挙げた手すりのほか、将来のリフォームを最小限にすることを考えたとき、どのような部分が検討候補に挙がるのかピックアップしました。
少しの力で開閉できるスライドドアにする
少しの力で開閉できるスライドドアは、年齢に関係なく日常生活の快適度アップに貢献します。
ドアを開いたままにできるため風通しの調節に使えますし、子どもから目を離してはならないときにも無理なく様子をうかがえます。ドアの開閉による騒音も起こらず、ゆっくり閉まるドアを選べばケガのリスクも減らせる点で魅力的です。
ドアを前後方向に開閉する必要がないため、高齢者に限らず移動にかかる負担軽減を実感できますし、車いすでも通りやすいという利点があります。解放感や視認性の確保、バリアフリーを重視している場合には、家づくりの段階からスライドドアの導入を検討しても良いでしょう。
ヒートショック対策として温熱環境に配慮する
寒暖差のある空間を移動することで血圧が急激に変化し、めまいや立ちくらみなどを誘発する「ヒートショック」をご存知でしょうか。
短期的な血圧の上下が主な原因とされており、冷えた浴室から温かい浴槽に移ったときや、暖かいリビングから寒いトイレへ移動したときなどに発生します。軽症であればめまい程度ですが、重症になると脳卒中や心筋梗塞に発展するため油断してはならない現象なのです。
ヒートショックによる死亡者数に公式情報はありませんが、浴槽における死亡者数は2019年時点で4,900人にのぼり、このうちの相当数がヒートショックを原因とする溺死ではないかとする意見もあります。
 Click here to add your own text
Click here to add your own text
出典:消費者庁「冬季に多発する高齢者の入浴中の事故に御注意ください!」
実際、消費者庁が公表する別のデータによると冬季に死亡者数が増加しており、ヒートショックが発生しやすい時期と被っています。ヒートショックは高齢者に起こりやすいのですが、実は以下のようなケースでも発症が見られており、年齢にかかわらず注意すべき現象とされています。
- 高血圧・糖尿病などを患っている場合
- 浴室・脱衣所が冷えている場合
- 熱い湯に長時間浸かった場合
- 飲酒直後に入浴した場合
- 肥満気味である場合
高齢者でなくても上記に当てはまればヒートショックのリスクが高まるため、若い人であっても決して油断できないのです。ですから、家づくりの段階から全室の温熱環境に配慮し、部屋ごとの寒暖差を抑えられる設計とすることも検討してみてください。
まとめ
「いま」だけに着目した家づくりと、「いま」と「将来」の両方に着目した家づくりでは、リフォームにかかる費用やリフォームで実現できる空間に違いが生まれます。マイホームに長く住めば、ほぼ確実に家族構成やライフスタイルが変わるタイミングが訪れるため、将来的なニーズを先回りした行動が望ましいでしょう。 本記事では一般的に起こり得る可能性を中心に取り上げましたが、家づくりのまえに家族全員で「将来どうなる可能性があるか」を話し合えば、さらに具体的なビジョンが浮かぶかもしれません。家づくりは人生における一大イベントであるため、できる限り後悔が生まれないように長期的な視点を持って臨んでみてください。


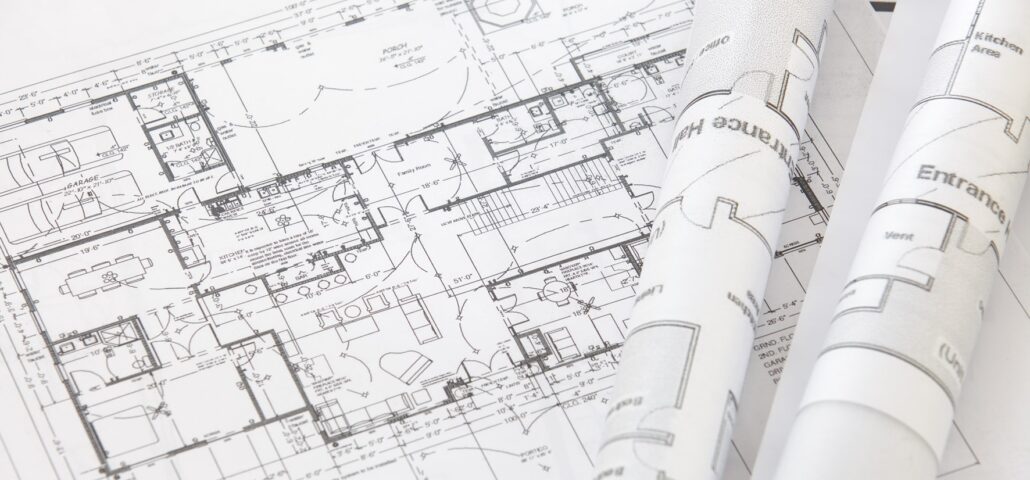











について-180x180.jpg)