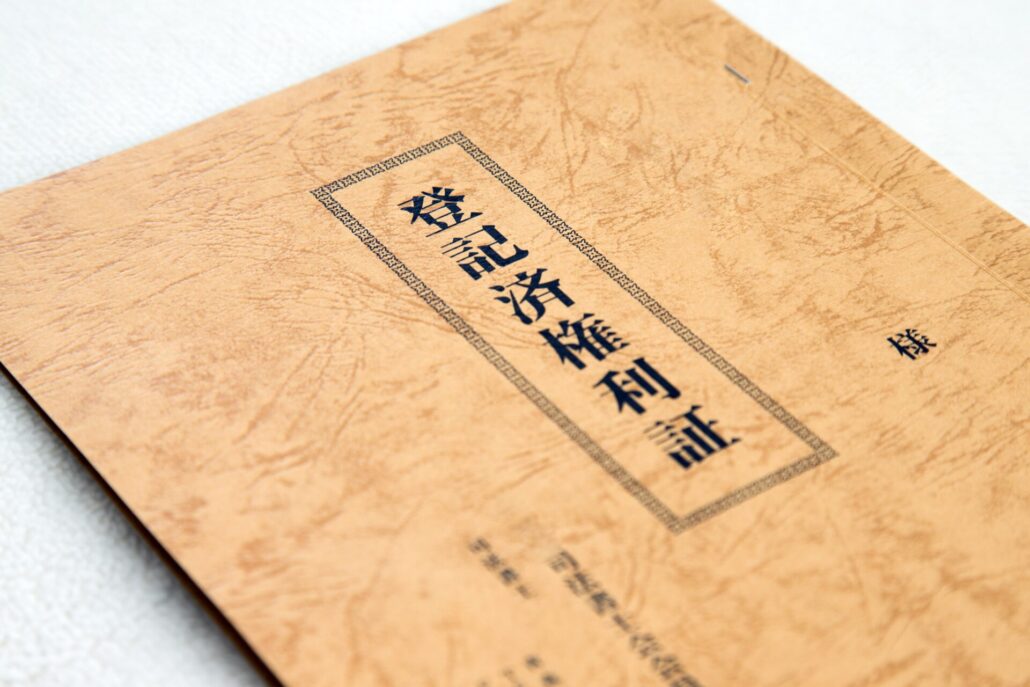【夫婦の住宅購入】住宅名義は一人が良い?共有名義が良い?メリットとデメリット
住宅名義を一人にするか、共有名義にするか迷ってはいませんか?
ここでは、住宅名義は一人が良いのか夫婦共同名義が良いのか、それぞれのメリットとデメリットをご説明します。名義人の人数が違えば適用される控除の上限が変わったり、相続時に懸念されるトラブルが増えたりするため、ぜひマイホームの取得前にご一読ください。
住宅名義における「単独名義」と「共有名義」とは
住宅名義において、一人の名義を登記することを「単独名義」、複数名の名義を登記することを「共有名義」といいます。たとえば夫婦のうち夫、あるいは妻のどちらか一人の名義で住宅ローンを組んだ場合、単独名義となり登記対象となる住宅にまつわる権利は名義人のみに与えられます。 一方、夫婦二人の名義で住宅ローンを組んだ場合、共有名義となり権利を有するのは夫・妻の二人です。支出した金額が違っても共有名義にはなりますが、持分割合は支出した金額の割合によって決まります。 一見すると、単に名義人が一人であるか二人であるかのみの違いに思えますが、単独名義と共有名義にはそれぞれメリットとデメリットがあるため解説していきます。
夫婦の共有名義で住宅を取得するメリット
夫婦が共有名義で住宅を購入する際のメリットは、大きく4つ挙げられます。
- 住宅ローンの借入額を増額させられる
- 住宅ローン控除が夫婦ともに適用される
- 売却時の特別控除が夫婦二人に適用される
- 相続税の節税につながる
このほか、共有名義にすることで夫婦二人の名前が登記されるため「夫婦二人の住宅である実感が湧きやすい」といったささやかなメリットもありますが、ここではあくまで金銭的なメリットに焦点を当ててご説明します。
住宅ローンの借入額を増額させられる
夫婦のうちどちらか片方が住宅ローンを組む場合、住宅ローン借入金額は一人の収入によって判断されます。
たとえば夫の年収が400万円の場合、夫一人が名義人となって住宅ローンを組む際には、審査は「年収400万円」という数字を判断材料として行われます。一方、妻の年収も400万円だった場合、夫婦二人が名義人となることで「年収800万円」として扱われることとなり、審査が有利に進むケースがあるのです。
住宅ローン控除が夫婦ともに適用される
単独名義であれば、住宅ローン控除が適用されるのは名義人一人だけですが、共有名義にすると夫婦二人ともが住宅ローン控除を活用できます。
住宅ローン控除は住宅ローンを活用してマイホームを購入したり、リフォーム工事を行ったりしたときに適用される税額控除の制度です。年末ごとに、住宅ローンの残額の1%にあたる金額を控除できます。
ただし、住宅ローン控除はどのような場合であっても利用できるわけではなく、国税庁が公開するページに記載されているように、以下を始めとする複数の適用要件を満たさなければなりません。
- 新築、または取得日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用年度の12月31日まで住んでいる
- 住宅の床面積が50平方メートル以上あり、床面積の2分の1以上が居住の用に供するものである
- 住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下である
- 10年以上にわたり分割して返済する住宅ローンであること
参考:国税庁「認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
適用要件に使われている「居住の用に供する」とは、その住宅に住むことを指しています。
なお、上記は新築住宅を取得する場合の適用条件であり、中古住宅の場合には「築20年以下(耐火建築物であれば25年以下)であること」や「生計をともにする親族などからの取得でないこと」などの条件が加わります。
そのため住宅ローン控除の利用時には、国税庁のページから最新情報を確認したり不動産業者に直接相談したりして、その時点における正確な適用要件を確認しましょう。
売却時の特別控除が夫婦二人に適用される
マイホーム(居住用財産)を売却した際には、所有期間にかかわらず譲渡所得(売却により得た所得)から最大3,000万円を控除できます。この控除は、居住用財産の各所有者に適用されるため、夫婦二人の場合には夫と妻にそれぞれ3,000万円の控除枠が与えられるのです。
単独名義であれば、譲渡所得のうち3,000万円を超える金額には税金が課せられますが、共有名義により夫婦二人で住宅を取得・所有していれば課税金額を抑えられます。
相続税の節税につながる
単独名義であった場合、名義人が亡くなり相続が生じた際に「名義人が保有していた不動産」の評価額が課税対象となります。
対して、共有名義により夫婦二人が名義人となっていた場合、一方が亡くなり相続が生じた際に課税対象となる不動産評価額は、被相続人(亡くなった人)が保有していた割合に応じた金額となります。そのため、単独名義よりも共有名義の方が相続税の負担は小さくなるのです。
夫婦の共有名義で住宅を取得するデメリット
夫婦が共有名義で住宅を購入する際のデメリットは、大きく3つ挙げられます。
- 売却時には名義人全員の同意が必要となる
- 相続により共有者が増えて意見統一が難しくなる
- 離婚した場合に売却しなければならない可能性がある
いずれも、必ずトラブルにつながるわけではありませんが、夫婦間や親族との関係性によっては面倒な事態につながります。それぞれ、どのような問題を引き起こすデメリットであるのかご説明します。
売却時には名義人全員の同意が必要となる
共有名義でありながら住宅を売却する場合には、夫婦のどちらかに権利を譲渡して単独名義にするか、共同名義のまま売却することになります。夫婦のうちどちらか一方が、共有名義の住宅に関して「自分の持分だけを第三者に売却する」というケースは非現実的です。
このような前提があるため、住宅の売却時には夫婦二人ともが売却に同意し、しかるべき対応をとらなければなりません。万が一、夫婦間の意見の不一致により売却が進まない場合には、売却したい名義人が売却を拒否している名義人を説得する必要があります。
売却時の同意の必要性は、一方の独断による現金化を防げる観点からメリットとして捉えることもできますが、これらを理解したうえで夫婦にとって公平な選択をすべきでしょう。
共有名義のメリットとして相続時に節税効果があることを紹介しましたが、相続人が複数いると夫婦二人の共有名義であったものが複数人に増えてしまい、売却時に全員の同意を取得しなければならないなどの懸念点があります。この場合、夫婦二人が同意して売却を決めるより、意見の統一が難しくなる可能性があります。
離婚した場合に売却しなければならない可能性がある
もしも夫婦二人が離婚した場合、マイホームを二分割にしてそれぞれが住むことはできません。
どちらか一人がもう一人から残りの持分を購入できれば、購入した側は引き続き家に住み続けられますが、マイホーム取得から日が浅ければ購入額は高額となります。そもそも、住宅の一括購入が難しいからこそ住宅ローンを利用するため、夫婦のどちらかが片方の持分を買い取れるほどの現金を持っているケースはまれでしょう。
このように、どちらか一方がすべての持分を買い取れるほどの現金を持っていない場合、家を持ち続けることができずマイホームを売却することとなります。
共有名義にする場合の注意点
共有名義で住宅を購入する場合、住宅を登記するときにそれぞれの持分を決めることとなります。
この際、住宅取得に充てた金額の割合に応じて、各々の持分が決まります。そのため、夫婦で半分ずつ資金を出し合ったなら持分は50対50ですし、夫が70%、妻が30%の資金を支出したなら持分は70対30に設定しなければなりません。
仮に、持分を支出の実態とは異なる割合に設定した場合、夫婦のうち資金を多く出した者から、もう一方への贈与とみなされる可能性があるため注意してください。
まとめ
住宅名義が一人(単独名義)である場合と、夫婦二人の共有名義である場合におけるメリット・デメリットをご説明しました。
結論としては、より大きなローン額を引き出したかったり各種控除を受けたりしたい場合には、共有名義が有力候補に挙がると判断できるでしょう。一方、将来的に夫婦仲が悪化したり、相続時に関係者とトラブルになったりするリスクを考慮するなら、単独名義の方が面倒な事態になりづらいと判断できます。
住宅の購入は人生のなかでもとくに大きなライフイベントですし、支出が高額なだけに後戻りができない側面もあるため、住宅名義については慎重に検討することをおすすめします。